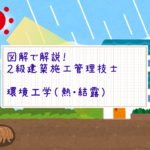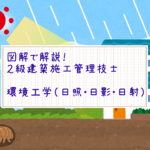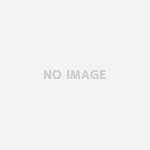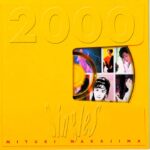この記事では、2級建築施工管理技士の環境工学 – 採光・照明の勉強方法と解説をしていきます。
暗記が必要になる内容が多いですが、図解付きで解説していくので、意味を理解しながら覚える事が出来ます。
また、照度基準など、数字を覚える必要がありますが、試験の傾向を見て重要度の高いものだけを解説しますので、効率的に勉強することが出来ます。
目次
環境工学 – 採光・照明とは
採光と照明はどちらも光を取り入れることですが、明確な意味の違いがあります。
意味が全く異なるので、履き違えないように覚えましょう。
照明 ・・・ 人口の光源(ライト・電球等)によって照度を得ること
照度とは
照度に関する用語として、照度・光束・光度・輝度があります。
各用語の意味の間違いが生じやすいため、絵で解説します。

採光とは
採光とは、昼間の太陽によって照度を得ることです。
太陽の光を昼光といい、昼光ではこちらで紹介した2種類があります。
天空光 ・・・ 太陽光が大気中で拡散した光のこと
昼光に関する用語も覚えていきましょう。


採光を効率的に行うために、トップライトが使われることがあります。
トップライトの採光効果は、側窓の3倍の採光効果があるんです!
また、建築基準法で、建物の用途や使用する場所によって照度基準が決まっていますので、試験に出やすい照度基準をピックアップして紹介します。

照明とは
照明とは、人工光源(照明器具など)によって照度を得ることです。
メリットとして、自然採光に比べて一定の明るさを保ちやすいです。
色温度によって、色みが変わる特徴があります。
出典:PHOTOGRAFAM
直接照明と間接照明
直接照明による陰影は、間接照明よりも濃くなります。
読書するとき、影が被さって読みにくかったことはありませんか?
設計時には、陰影に注意する必要がありますね。
出典:ushigyu.net
光天井照明
光天井照明は、室内の照度分布が均等になり、照明による影がやわらかくなるメリットがあります。
全般照明と局部照明
全般照明と局部照明をどちらも使用する場合は、全般照明の照度は、局部照明の1/10以上にすることが良いとされています。
暗記が必要になる内容が多いですが、意味を理解しながら覚えることで、知識が定着しやすかったのではないでしょうか。
意味の履き違えがないよう、ときどき復習することが大切になります。
それでは、ご安全に!