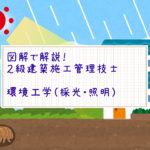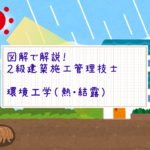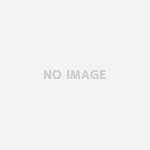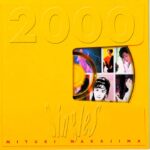この記事では、図解で2級建築施工管理技士の環境工学 ‐ 日照・日影・日射の勉強方法と解説をしていきます。
例年の試験に出題されているため、重要度は高いので、しっかりと勉強していきましょう。
目次
環境工学 - 日照・日影・日射とは
日本には四季があり、南北に細長く起伏が激しいため、自然環境は豊かな地形です。
そのため、人々が快適に、そして安全に暮らせる建物を考える必要があります。
日照
日照とは、太陽の直射日光が地面に当たっている状態のことです。
居住する家において、できるかぎり日照を確保する必要があります。
また、日照率は日照時間÷可照時間×100(%)で求めることが出来ます。
 上の写真の場合、可照時間は7時〜19時の12時間で、
上の写真の場合、可照時間は7時〜19時の12時間で、
日照時間は7時〜13時,16時〜19時の9時間です。
日照率は、9時間(日照時間)÷12時間(可照時間)×100%=75%
になります。
日影
日影を作るのは、太陽があるからです。そこで、太陽について詳しく見ていきましょう。

・太陽の位置は、太陽高度と太陽方位角で示されます。
・太陽が真南に来た時の高度のことを、南中高度といいます。
・建物によって終日、日影になる場所を終日日影と言います。(そのままですね。。。)
また、夏至のときでも終日日影になる場合、永久日影と言います。
夏至(1年の中で最も可照時間が長い日)に終日日影になる=その場所は一生日が当たることはないでしょう。
日射
日射とは、太陽が放射するエネルギーのことです。
単位面積(㎡)が単位時間に太陽から受ける放射エネルギーの量を日射量と言います。
太陽の放射エネルギーが直接地表に当たる日射量のことを、直達日射量といい、太陽の光が大気中で拡散して地表に届く日射量のことを天空放射量といいます。
直達日射量と天空放射量を合計したものを、全天日射量といいます。
夏は直達日射量を減らし、冬は直達日射量をできる限り取り入れると、住居環境が良くなります。
暑い夏には、直接当たる太陽の光を極力遮り、寒い冬には直接太陽の熱を取り入れることが大切だからです。
太陽の透過率が高いほど、直達日射量が強くなり、天空放射量は弱くなります。
中国をイメージして欲しいのですが、中国は大気汚染により空気が汚れていますよね。
ひどい時期は10m先が見えなくなる状態でした。
そんな状況では、太陽の光が直接当たる量が減りますよね。
直達日射量は、季節によって大きくなる位置が変わります。
夏季は、水平面>東・西面>南面>北面の順番で大きくなり、
冬季は、南面>水平面>東・西面の順番で大きくなります。
この順番は、試験の頻出問題ですので、しっかりと覚えましょう。
覚え方のコツとして、語呂合わせを紹介します。
日照・日影・日射は設計的な部分が強いですが、日常に大きく関わっていることですので、役に立つ事があると思います。
また、試験において頻出問題でもあるため、しっかりと勉強し、点を取れるようにしておきましょう。
それでは、ご安全に!